住宅ローン控除が残っているけど繰り上げ返済すべき?
最近、住宅ローンの金利上昇を受けて、繰り上げ返済を検討する方が増えています。
ただ、「住宅ローン控除もあるのに、本当に今返してしまって大丈夫?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローン控除期間中に繰り上げ返済をするべきかどうかを、金利や控除率との関係からわかりやすく解説します。
本記事の最後には、手元資金は残して置きたいけど、月々の返済額を減らした方への案内もあります!
元銀行員の視点から実体験に基づいてご紹介しますが、最終的な判断は専門家への相談やご自身の状況をふまえてご検討ください。
結論:あなたの状況次第で“今”か“待ち”かが変わる!
住宅ローンの繰り上げ返済を考えるとき、住宅ローン控除とのバランスが非常に重要です。
そこで、「返済した方が良いケース」と「控除期間が終わってから返すべきケース」について、それぞれの背景や典型的なライフスタイルも交えて、詳しく解説します。
繰り上げ返済した方が良いケースとは?
1. 借入額が控除の上限を超えている場合
住宅ローン控除は残高すべてが対象になるわけではなく、上限があります。
例えば、新築の認定住宅などであれば上限5,000万円、それ以外では3,000万円などと決められています。
例:4,500万円の借入をしている方が、控除上限が3,000万円の場合
→ 残り1,500万円分には控除が適用されないため、早めに返済した方が利息軽減のメリットが大きくなります。
2. 住宅ローン金利が控除率(0.7%など)を上回っている場合
控除率を超える金利を払っている場合、単純に損失が出ている状態です。
特に、固定金利で2%以上の金利で借りている方は、0.7%の控除ではカバーしきれず、「支払い利息 > 控除額」となるため、繰り上げ返済の検討余地があります。
3. 控除が満額使いきれない場合(税額が少ない)
住宅ローン控除は「所得税+住民税」から差し引かれます。
しかし、たとえば以下のような方は要注意です。
- 育休中・パートタイムで収入が少ない
- 控除対象外の所得控除(医療費・扶養など)で課税所得が小さい
- 配偶者控除やiDeCo、ふるさと納税など他の控除が重なっている
このような場合、「そもそも控除があまり使えない」=節税効果が小さいため、メリットを感じづらく、繰り上げ返済の方が利息軽減でトクになることもあります。
控除期間終了を待った方が良いケースとは?
1. 金利が控除率よりも低い(変動金利など)
現在は変動金利0.3〜0.5%という超低金利の時代。
一方で、控除率は0.7%(2022年以降の入居者)。
この場合、「金利より控除の方が大きい」=実質的に得をしている状態になります。
繰り上げ返済してしまうと、この“得”を捨ててしまうことになるため、焦って返すのはもったいない場合があります。
2. 控除額をしっかりフルで受けられている
たとえばサラリーマンの方で、年収500万円以上・扶養控除が少ない・副収入などもある方は、所得税・住民税がしっかりかかっています。
その場合、住宅ローン控除の節税効果をフルに享受できるため、控除期間中はローンを維持する方が合理的です。
3. 手元資金に余裕がない
繰り上げ返済は資金が必要です。ですが、生活費がギリギリ、あるいは子どもの教育費・車の買い替え・介護など、将来的にお金が必要になる可能性がある方は、むやみに返済せず、資金を手元に残す判断も重要です。

私が銀行員時代、毎月の住宅ローンを多めに返済していた方がいたけど、車を購入するのに手元資金が足りなくなって、金利が高い自動車ローン(当時の金利約3〜5%程度)を借りようとしていたケースがありました…
住宅ローン控除についておさらい
ここで、住宅ローン控除について簡単におさらいしておきましょう
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税や住民税が減税される制度です。
つまり、ただでさえ金利の安い住宅ローンに対して、さらに「税金を安くしてくれるボーナス」のような存在。
この制度を上手に活用することで、実質的に住宅ローンの負担を軽減することができます。
具体的にはどうやって控除されるの?
年末時点の住宅ローン残高に、所定の「控除率」をかけた金額が、翌年の所得税から差し引かれます。それでも引ききれなかった分は、住民税からも一部控除されます。
例えば、住宅ローン残高が2,000万円あれば、
- 控除率1%の場合:年間20万円の税金が戻る
- 控除率0.7%の場合:年間14万円が戻る
といったイメージです。
この金額が10年〜13年続くため、トータルで100〜200万円以上お得になるケースもあります。
制度の概要(表で確認)
| 入居時期 | 控除率 | 控除期間 | 所得制限 |
|---|---|---|---|
| 2021年まで入居 | 1.0% | 10年または13年 | 3,000万円 |
| 2022年以降入居 | 0.7% | 13年(新築) 10年(中古) | 2,000万円 |
※2021年以前の入居者は、2022年以降も引き続き従来制度(1.0%)が適用されます。
よくある誤解
「控除額が戻ってくる=現金でもらえる」と思っている方もいますが、実際は支払う予定だった税金が差し引かれるだけです。
あくまで“節税”であり、“収入”ではありません。
繰り上げ返済と控除、どっちが得?【金利との関係】
ここでポイントとなるのが、住宅ローンの実質金利が、控除率を上回っているかどうかです。
- 控除率(0.7%)> 実際のローン金利(例:0.5%) → 控除期間中は返済を遅らせたほうが得
- 控除率(0.7%)< 実際のローン金利(例:1.5%) → 控除期間中でも繰り上げ返済したほうが得
シミュレーション例
【前提】ローン残高:1,000万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間利息(0.5%) | 5万円 |
| 年間控除額(0.7%) | 7万円 |
| 実質的な“得” | +2万円 |
このように、「利息を払っても、税金の控除で上回る」状態、いわば“逆ザヤ”=マイナス金利状態になるケースがあります。
この状況なら、あえて繰り上げ返済せずに、控除期間が終わるまでそのまま返済を続けた方が金銭的に得になるのです。
返済するなら“1月”が最も効果的なタイミング
住宅ローン控除の適用額は、「その年の12月末時点のローン残高」に対して計算されます。
つまり、控除をきちんと受けたうえで繰り上げ返済したい場合は、「12月まで残高を維持 → 翌年1月に返済」がベストです。
タイミング別の注意点
- 12月に返済してしまうと?
→ 返済前の残高で控除が計算されないので、控除額が減ってしまう可能性あり! - 1月に返済すれば?
→ 年末残高が反映された控除を“まるごと”受けたうえで、利息も軽減できます。
特に、繰り上げ返済を予定している方は、1月〜2月頃の実行がベストタイミングと言えるでしょう。
注意!繰り上げ返済で失敗しないための3つのポイント
生活防衛資金は必ず確保しておくこと
これは最も大事な要素です!
繰り上げ返済で手元資金がなくなってしまっては、元も子もありません。
子供の教育費、自動車の購入、家の修繕、その他生活費など、万が一の出費に対応できるようにしておきましょう(繰り上げ返済でお金がなくなって、高金利の教育ローンや自動車ローンを組んでいては本末転倒です)。
最低でも生活費の6ヶ月〜1年分は、普通預金などですぐ引き出せる形で残しておきましょう。
他の高金利ローンがあれば、そちらを優先
住宅ローンはもともと低金利です。
もし以下のようなローンがあれば、先に繰り上げ返済するのはそちらかもしれません。
- 自動車ローン(2〜4%)
- 教育ローン(2〜3%)
- カードローン・リボ払い(10〜18%)
繰り上げ返済資金の使い道として、「より金利の高い借金から優先」が原則です。
金融機関の手数料・ルールも確認
繰り上げ返済には、ネット返済なら無料、窓口だと数千〜数万円かかるなど、金融機関ごとに違いがあります。
また、最低返済金額(10万円~100万円単位)や回数制限がある場合も。
手数料と利息軽減額を天秤にかけて、「本当にお得になるか」を確認しましょう。
まとめ:住宅ローン控除を最大限活かすには「賢い判断」と「適切なタイミング」がカギ
繰り上げ返済は、利息を減らせる魅力的な選択肢ですが、住宅ローン控除という“目に見えにくいメリット”を失ってしまうこともあります。
ポイントは次の3つ。
✅ 住宅ローン金利と控除率を比較する
✅ 控除を最大限受けてから返済する
✅ 手元資金や家計の余力をしっかり確保する
短期的な節約ではなく、10年以上先まで見据えて、家計にとって最も効果的な戦略を選びましょう。
最後に:手元資金を残して置きたいけど、月々の返済額を抑えたい方へ
「金利が高くなってきて返済額が増加するのは気がかりだけど、繰り上げ返済するほどにお金はないんだよなー」
という方は借り換えも選択肢になりうるかと思います。
ただ、借換前にぜひ、確認してほしいことがありますので、ぜひ下のリンクから記事を見てみてください!
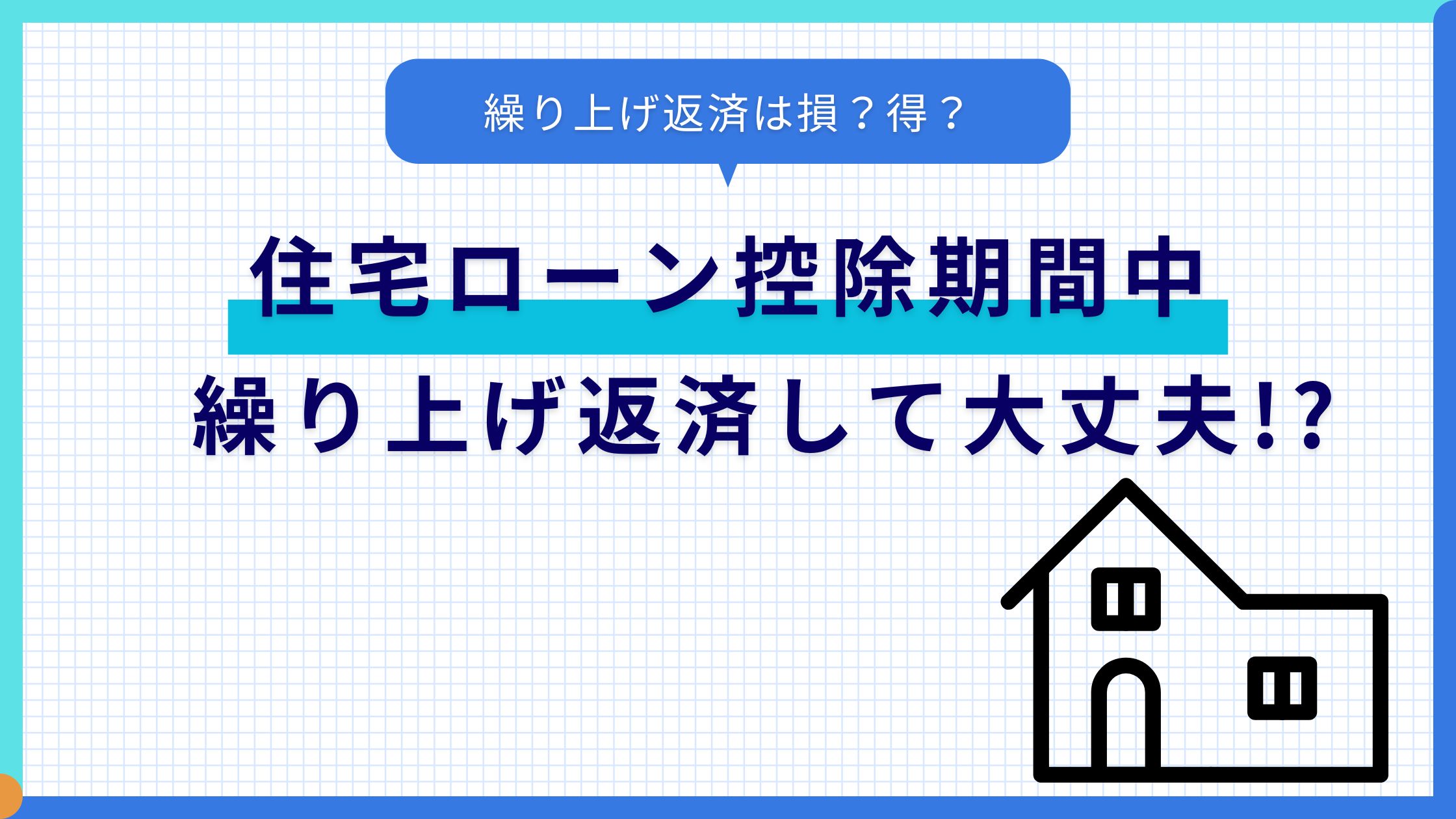

コメント